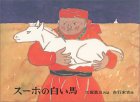
<「スーホの白い馬」/福音館書店>
●ファースト・インパクト
気がつけば、僕はもう9年もの馬齢を重ねてしまった(馬頭琴を手にして9年)。今でこそ僕の生活は大きく馬頭琴に依存しているけど、この楽器のことを最初に知ったのは、やはり子供の頃に読んだモンゴル民話「スーホの白い馬」だった。これはきっと日本人に一番多い「馬頭琴との出会い」の形だろう。なにせ、この物語の絵本は30年以上にわたってロングセラーを続ける日本の絵本の代表格だし、小学校の国語の教科書に載っていることもある。たくさんの日本人の記憶に、モンゴルに馬頭琴有り、と教え続けてきたのだ。ところが、意外に思う方もいるかもしれないが。実はこの民話、モンゴル国では、あまり知られていない。面白いことにモンゴル国では「白い馬」ではなく「黒い馬」が登場する全く別バージョンの馬頭琴伝説の方が有名である。すなわち、モンゴル国の一般の人にとって馬頭琴は知られていても、我らがスーホ君はあまりにも無名な存在なのだ。なぜ?と不思議に思う方は、モンゴル民族の住む地域が、実は世界にいくつかあるということを知っておかねばならない。そして、その中で代表的なのはモンゴル国=いわゆる「外モンゴル」と、中国内蒙古自治区=いわゆる「内モンゴル」であり、この「スーホの白い馬」は、主に内モンゴルの方に伝わっている馬頭琴伝説なのである。
さてそういう意味では、今回の内モンゴル訪問は、子供の頃に読んだ「物語の世界」に20数年越しにたどり着いた旅、とも言えるだろう。ならば、ついに「現実の世界」として眼下に広がる内モンゴルの、記念すべき最初の風景を、この眼にしっかりと焼きつけようじゃないか。ということで、エコノミークラスとは言えあまりにも狭い中華航空・国内線の機内で、こわばった体をよじり、窓に顔をぐっと近づけてみた。たしか、「スーホの白い馬」はこんな風に始まったはずだ。「中国の北のほうモンゴルには広い草原が広がり、そこに住む人たちは昔から、羊や山羊、馬などを飼って暮らしていました・・・」さぁ、もうすぐフフホト空港だ。眼下にはどんな広い草原が広がっているだろうか。
.jpg) ・・・眼に映ったのは、夕陽に赤く照らされた、広大な、非常に大陸的な風景だった。ところがよく目を凝らすと、その眺めはかつてトゥバに行った時に上空から見た南シベリアの大草原や、ウランバートル行きの飛行機から見た外モンゴルの大草原とはまるっきり異なるものだった。この辺りの平地という平地は、すべて幾何学模様に埋め尽くされている。大規模な農業地帯が広がっているのだ。内モンゴルには多くの漢民族が移住して農業も行なっている、ということはいろんな本に書いてあるからさすがに以前から知ってはいた。しかしまさかこれほどの規模で、農場というタイルが敷き詰められているとは思ってもみなかった。初めて自分の眼で見た内モンゴルの現実の風景。今回の旅の始まりを告げる最初の衝撃であった。
・・・眼に映ったのは、夕陽に赤く照らされた、広大な、非常に大陸的な風景だった。ところがよく目を凝らすと、その眺めはかつてトゥバに行った時に上空から見た南シベリアの大草原や、ウランバートル行きの飛行機から見た外モンゴルの大草原とはまるっきり異なるものだった。この辺りの平地という平地は、すべて幾何学模様に埋め尽くされている。大規模な農業地帯が広がっているのだ。内モンゴルには多くの漢民族が移住して農業も行なっている、ということはいろんな本に書いてあるからさすがに以前から知ってはいた。しかしまさかこれほどの規模で、農場というタイルが敷き詰められているとは思ってもみなかった。初めて自分の眼で見た内モンゴルの現実の風景。今回の旅の始まりを告げる最初の衝撃であった。
.jpg)
(そして、これから続く旅の途中で、何度も何度も思い起こされる極めて象徴的な風景なのだった。)
All rights reserved.
のどうたの会 (c) The Throat-Singing Soceity, Japan
嵯峨治彦
SAGA Haruhiko thro@sings.jp