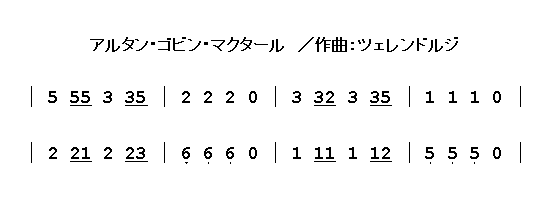●ツェレンドルジ
最終日(8/4)はツェレンドルジ(65)の登場。お名前と写真、そして演奏しているご様子は、本やらテレビやらで何回か見たことがあると思うんだが、具体的には馬頭琴弾き語りのマクタール(賛歌)・ユルール(祝詞)の名手である、ということ以外はほとんど何も知らなかった。そういう、ある意味ではノーマークな演奏家だったのだが・・・、いやぁ、彼もまた実に素晴らしいライブをしてくれた。最終日を飾るにふさわしい名演奏であった。お見事!プロフィールとしてはこんな感じ。
・1940年、ゴビ生まれ
・モンゴル国立大学文学部卒
・言語学博士
・25才から賛歌の作詞作曲を始める
・ガビヤット(人間国宝)
・ブリヤートの馬頭琴普及にも努める
・現在はウランバートルに暮らすちなみに彼は、モンゴルの1年を始める馬頭琴を弾いているそうだ。つまり、正月の午の刻、ツェレンドルジの馬頭琴がTVで放送されるのだそうだ。大御所なんだなぁ。
一緒に息子と娘が来ていたが、息子のソヨルエルデネは馬頭琴奏者で、日本に留学して三味線を学んだりしているという。そのためか、ツェレンドルジご自身も、日本人が馬頭琴をやることを好意的にとらえているようだった。
ライブ前の夕食の席でツェレンドルジ親子と同席したんだが、ツェレンドルジは、目鼻立ちがハッキリしていて俳優の萩○健一によく似ている男前。日本語が分からないのをいいことに「いやぁショーケンに似てるよねー」なんて日本人同士で話してたんだが、実は娘と息子は日本語が少し分かるそうだ。ありゃりゃ。「ショーケン」って単語知ってるかなぁ。
さて、彼もまた完全なソロライブはほとんど初めてのことだそうだ。それで今日は念入りに用意した珠玉のレパートリーを丁寧に聞かせて頂けるのだった。 (ライブ中の撮影・録音は不許可だった。)
■「ゴビ賛歌」
1964年に南ゴビの文化会館で作った曲を、馬頭琴の弾き語り。
このゴビ賛歌はネルグイさんも良く歌うし、僕も日本語版を作ってライブでやってるんだけど、なんとこの曲を作ったのはこの人だったのか!渋くて深い良い声である。演奏中の顔の表情の付け方などは、社会主義時代のミュージシャンという感じで、大舞台でも映える感じ。威風堂々。
ちなみに左手の指使いはネルグイ奏法と同じく、親指多用、薬指が外弦をくぐる。ライブの後で質問したところ、昔はこうやって弾くのはめずらしくなかったようだし、彼自身も「これは弾きやすい」と言っていた。今回出演できなかったダギーランス(中央ゴビ)も同様に弾いていたし、西村さんの持っているある別の遊牧民馬頭琴奏者の写真にもこの弾き方が見られる。弾き語りをする上で弾きやすく、また独特のノリが出せるこの奏法、もしかしたら馬頭琴が近代化する過程で「メロディ楽器」的な側面が偏重されるあまり、結果的に見落とされてしまったのだろうか。
■「英雄叙事詩」
トプショールをはじきながら素の声とハルヒラー(モンゴルの重低音喉歌)で歌う。
これもライブ終了後に聞いたんだが、ゴビにはハルヒラー等喉歌はもともとないそうだ。余談になるが、彼のトプショールにはビックリ!
楕円形のボディで、革張りの表面板なんだが、その革の縁を、アルハン模様がぐるりと取り囲んでいる。(下・左) これって愛用しているラーメン・トプショール(下・右)に激似じゃないか!( おうまさんといっしょ 「<13>ラーメン食べたい」参照 )




 ホーチル(四胡)の弾き語りで、個人を讃える歌を。だれか観客の中から選んで、その方を讃えようということになったが、せっかく選ばれたI川さんが「私なんて褒めるところないですから〜(笑)」とご辞退されたので、急遽代役としてニシムラさんが讃えられることに。
ホーチル(四胡)の弾き語りで、個人を讃える歌を。だれか観客の中から選んで、その方を讃えようということになったが、せっかく選ばれたI川さんが「私なんて褒めるところないですから〜(笑)」とご辞退されたので、急遽代役としてニシムラさんが讃えられることに。